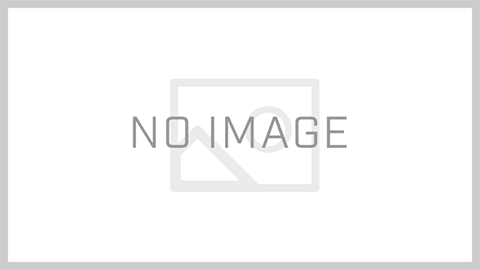目次
新卒3年目、コロナ禍でメンタルを崩しました
新卒3年目、コロナ禍の中で仕事で体調(メンタル面)を崩してしまいました。
会社のシステム運用の仕事についており、コロナ影響に伴う海外情勢の変化を受けまくりました。
日々、体制が変わり判断も変化し、心が休まる事が中々なく、ずっと自宅勤務で仕事環境も変化。
仕事量に対するストレスを上手く解消できませんでした。
苦しくてもなんとかいけるだろう、と思っていたのですが、突然仕事に向き合うと動悸が止まらない状態に。
精神的に限界がきていることを知りました。
頑張り屋・責任感が強めの人は、本当に気をつけた方が良いです。
今回は限界が来る前にストップをかけて、休息を取ることで回復を図ることにしました。
今後の仕事量について・自分のストレスの原因。
これらをしっかり休息する中で言語化していきたいなと思っています。
人生、幸福に生きれないと本当に苦しいですから。
仕事のキャパ = お酒への耐性
私が信頼しているコーチングを受けているコーチに相談をしました。
その中で「仕事」への向き合い方について「お酒」の比喩を使って語ってもらった見方がとても参考になったので紹介していきたいと思います。
(大前提として、ある程度お酒が飲めるという程で比喩を書いています。体質的に全く飲めない人も比喩として理解していただければ幸いです)
仕事のキャパシティは、お酒への耐性に例えることができます。
同じ仕事(お酒)でも、感じる負荷は人それぞれです。
元々持っている資質によって、大きくストレスを感じる人もいればあまり感じない人も世の中にはいます。
キャパシティは、お酒に慣れるようにある程度継続していれば増やすことも可能です。
ですが、お酒が沢山飲める人と飲めない人がいるように、それぞれの人が持つキャパシティには限りがあります。
厳しい現実かもしれませんが、努力量だけでは乗り越えられないこともあります。
ないということで耐性が、同じようなキャパシティを持っている人と比べてしまうのは意味がないし、自分を苦しめてしまうだけです。
「お酒飲めないのはだめだ!」とは言わないですよね?
それで無理をして取り組んでも、身体が拒否をして時と場合によっては死に綱がってしまいます。
それは仕事も同じなのです。
大事なのは、お酒のキャパシティを理解するように自分の仕事に対するキャパシティを知ることです。
仕事=お酒 得意/不得意が人にはあるから、自分に合ったお酒を選択する。
仕事に対するキャパシティを知ること。
それは、自分が得意/不得意と感じるお酒を知り、自分にあったお酒との付き合い方を知るのと似ています。
アルコール度数が高いお酒、
味が甘かったり苦かったりするお酒、
いろいろと世の中にはあります。
それは仕事の種類の選択においても同じです。
ビール(仕事の種類)が得意で、ビールならば飲める量が多い人もいます。
逆に、お酒(仕事)は飲めるけれどビールは受け付けない人もいます。
キャパシティが大きくても最大限に活きていないお酒の選択をしている場合も往々にしてあるはずです。
ほとんどの人は、そこまでお酒(仕事)の種類に触れ合う機会は少ないはずです。
自分が知らないカクテルと出会ったら、ばっちりあって飲めるキャパシティも想定していたよりも多いこともあるかもしれません。
得意/不得意は必ずあります。
自分にあったお酒(仕事)を選択していきましょう。
自分の仕事=お酒のキャパシティを知り、「No」と言えることが最も大事
仕事(お酒)との向き合い方で一番大事なこと。
それは、キャパシティを知った上で超えそうな時に「No」と言えることです。
キャパを超えてお酒を飲み過ぎると人は簡単に倒れてしまいます。
消化しきれなかったお酒は、自分を蝕み、体調悪化から引いては死にいたらしめる可能性もあります。
まず大事なのは、お酒をジョッキ1杯しか飲めない自分を受け入れること。
そこは否定をしてはいけません。
無理をすることが一番、自分を殺してしまう。
飲めるキャパシティで自分はどうできるのか?
受け入れた上で、自分に合ったキャパシティをもとに
自分が価値を出せる仕事に取り組んでいくこと。
それが大事です。
お酒が苦手な人であれば、「ここまでしか飲めないんだ」とか「今日は飲まない」と言えますよね?
それと同じく、仕事もNoということが大事です。
実際に自分はYesと言い続けて、自分が抱えきれず消化できない仕事に殺されかけました。
未消化なお酒(仕事)が忙しさと相まって、自分に大きな負担を与えていたのです。
Noというのはとても難しいです。
ですが、日々の中で何がストレスになっているのか?をしり、
自分の仕事(お酒)のキャパシティを理解して、今後どう仕事に向き合うか?を考えることは、幸せに働き、生きる上で大切なことです。
このお酒の比喩が考えるきっかけになれば幸いです。